クオリティメディアコンソーシアム
BI.Garageが有力メディア30社と共同運営し、日本のデジタル広告の品質の改善に注力する組織。広告掲載メディアと掲載広告双方のクオリティを追求できる唯一の広告配信ネットワークとして、最高品質の広告の提供を強化している。
*クオリティメディア宣言について
Designing
New Context
Designing
New Context
| フェイクニュースや生成AIを悪用した記事など悪質なメディアが氾濫するインターネット環境で、今「デジタル広告」が果たすべき役割、そして求められる変革とは?良質なメディア環境の実現を目指す広告・メディア企業が立ち上げた「クオリティーメディアコンソーシアム」に加盟する各社へのインタビューを通じ、その課題と未来を連載していきます。 |
民主主義は今、瀬戸際にある——。田北浩章氏(東洋経済新報社代表取締役社長)と長澤秀行氏(BI.Garage社 特命顧問)は、インターネット広告市場の現状から警鐘を鳴らす。ネット広告を取り巻くエコシステムに複数の悪因がある上、企業が無意識に悪質なメディアに広告を掲載してしまう状況が生まれ、ジャーナリズムに真摯に取り組むメディアが力を失いつつあるからだ。
そんな環境を変えようと2023年10月、デジタルガレージグループで最先端のWeb広告技術の開発と販売を行うBI.Garageがメディア30社と運営するクオリティメディアコンソーシアムは、「クオリティメディア宣言」を発表した。代表幹事の田北氏と団体を主宰する長澤氏に、その背景と目指すべき未来を議論していただいた。
株式会社東洋経済新報社 代表取締役社長
田北 浩章
1985年東洋経済新報社入社、1999年「ベンチャークラブ」編集長、2005年「会社四季報」編集長、2011年取締役編集局長、2016年常務取締役、2018年常務取締役ビジネスプロモーション局長兼デジタル事業本部長2020年専務取締役、2022年12月より現職。TBS系「がっちりマンデー!!」(日曜朝7:30~8:00)コメンテーター(年1回「僕たち上場しました」特集に出演)。
株式会社BI.Garage 特命顧問
長澤 秀行
1977年(株)電通入社、新聞局デジタル企画部長を経て 2004年 電通 インタラクティブコミュニケーション局長、2006年 ㈱サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS)代表取締役社長CEO 2014年一般社団法人日本インタラクティブ広告協会常務理事。2017年より(株)デジタルガレージ特命顧問。2020年同社グループの(株)BI.GARAGEの取締役に就任。同社にて日本国内の30媒体社からなる「クオリティメディアコンソーシアム」の事務局長としてコンテンツメディアの価値を活かしたデジタル広告事業を推進。
田北:そもそも「インターネットとはなにか」を考えますと、人類が初めて個々に向けて発信する手段を手に入れた。産業革命を遥かに凌駕するものだと考えています。しかしその繁栄の結果どうなってしまったかと言えば、我々のように「コスト」をかけて作ったコンテンツと、コタツ記事やフェイクニュースなどが全く等価になる世界が訪れてしまいました。予想はしていましたけれども、その想像を遥かに超える世界が今展開されています。
長澤:広告代理店の立場からお話ししますと、田北さんのおっしゃる通り「コスト」のかかる記事を作るメディアは、ネット広告市場において正当に評価されていません。なぜかと言えば、インターネット広告の価値評価の仕組みが「クリック至上主義」だからです。いわゆるマスメディアの視聴率、新聞や雑誌の発行部数などとは異なり、デジタルメディアに出稿される広告の閲覧数は評価されず、実際にクリックされて初めて価値が発生します。換言すると、ネット広告の、特にプラットフォーマーが提供する仕組み上では、コンテンツやメディアのクオリティや道徳的な良し悪しに対して無関心であり、広告が掲載さえすればなんでも構わないのです。

長澤:ネット広告の歴史を簡単に振り返りますと、私が電通で働いていた10年前のネット広告は、新聞やテレビなどのマスメディアと同じような販売方法でした。潮目が変わったのはGoogleやFacebookが台頭し、機械的な運用型広告の売買が始まった頃です。最近ではアテンションエコノミーと呼ばれますが、これは不道徳だろうが劣悪だろうが炎上しようが関係なく、ユーザーの興味関心を惹くコンテンツこそが良いという原則に基づいた広告運用の概念です。
さらにユーザーを追いかけ、クッキーに紐づくターゲティング広告を閲覧させられれば(行動ターゲティング広告)、どんなメディアに掲載されても良いということもある。これらのルールに則って、ウェブ広告は何百何千あるウェブサイトにばらまかれています。その結果が0.1%のクリックがあれば、残りの99.9%のユーザーがどう思おうが構わないという考え方です。これはものすごくユーザーを馬鹿にしている話で、これまでのマスメディア広告とは逆転した考えです。モラルの崩壊と言いますか、ユーザーがどのように興味や関心があるかを全然考えられていません。
長澤:現状のままでは、広告費で良質なコンテンツサイクルを支えていけないのではないかと考えました。広告自体のクリエイティブ表現のクオリティ云々がある一方で、広告の掲載先であるメディアのクオリティがあってこそ、広告の真価は発揮されます。この度発表した「クオリティメディア宣言」では、「良きコンテンツに良き広告が宿る」ということを言っているのですが、まさにこれに尽きます。良きコンテンツは良きメディアに宿り、良きメディアにはロイヤルユーザー(ロイヤル読者)の存在があります。
東洋経済さんをはじめ取材に手間暇をかけ、きっちり裏取りし、編集し、校正して世の中に良い記事を出す、もしくは意見を出す信頼あるメディアの先には、広告を含むコンテンツを評価する良きユーザーの存在があり、一連のエコシステムを評価する指標を設けなければ、高いクオリティのメディアは苦境に立たされると思います。
この先、生成AIなどによるフェイクニュースや広告はますます増えるでしょう。その際、世における情報の指針はどこが示すのでしょうか。決して広告のページビュー数ではありません。情報の指針は、しっかり取材されたコンテンツが世の中をリードしていかないといけない。まさしく「ジャーナリズム」たるものの果たす役割であり、これが果たせなければ民主主義的な社会の揺らぎが必ず起こります。
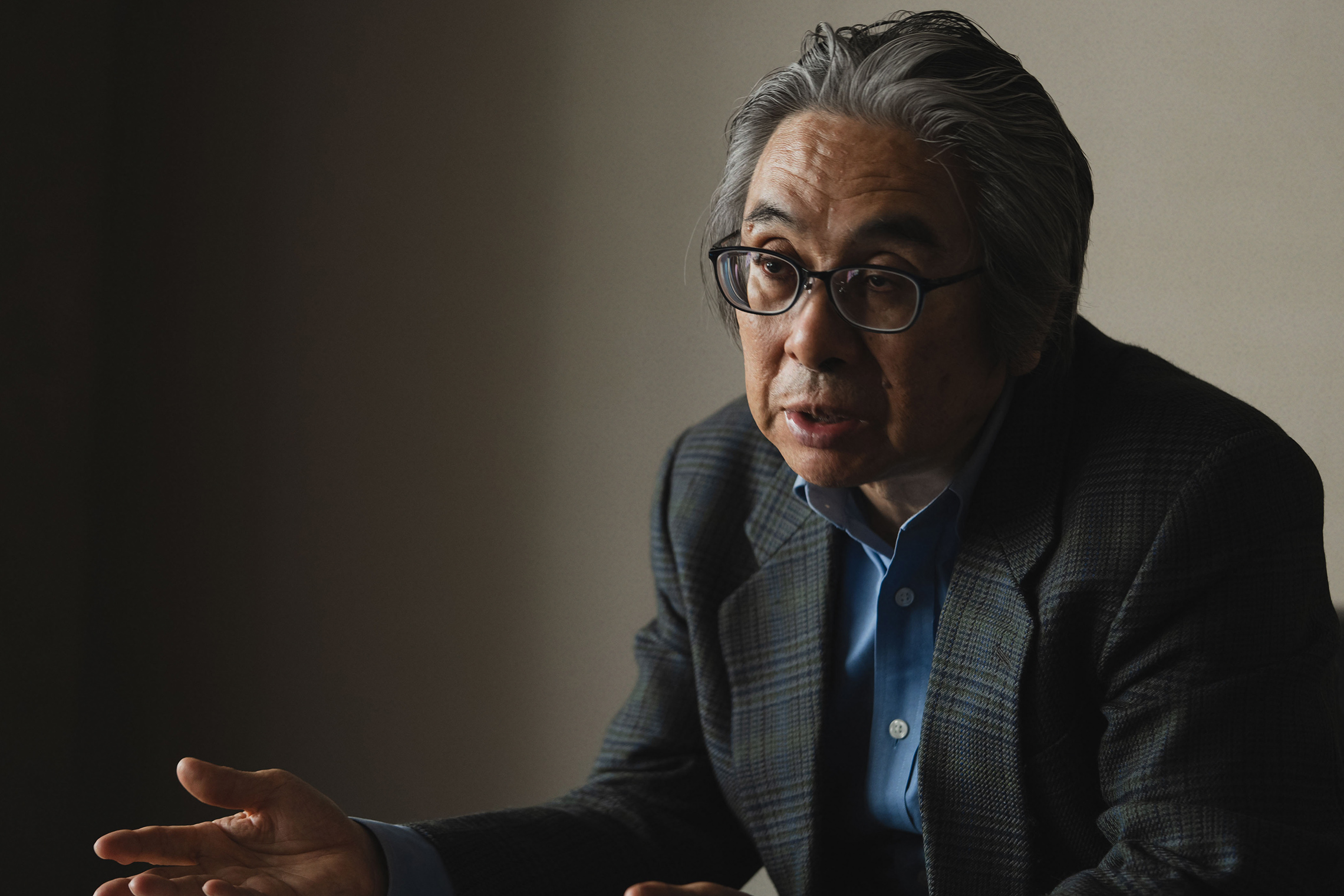
田北:長澤さんが民主主義とおっしゃいましたが、私もその点がすごく重要だと思います。冒頭に言及した「コスト」とは、民主主義のコストだというふうに読者のみなさんには思って欲しいです。「民主主義を維持する方が良いか?」という問いに対する答えがノーならば、我々のようにコストをかけるメディアは不要です。当社規模でも100名ほどの記者を抱え、外注をせず、自社の理念を理解する社内の人間が取材しています。適切不適切な表現を厳密に精査して記事の制作にあたっています。ジャーナリズムを体現するというのはそれ自体が相応のコストがかかるものだと言わざるを得ません。
民主主義国家では、こうしたコストをかけるメディアが発信する情報を見て、国民のみなさんが的確、適切に物事を判断して行動される。その方がおそらく幸せな世の中なのではないかと。ロシアや北朝鮮のような専制国家ではジャーナリズム的存在は求められませんので、もしみなさんと私たちとの間で、この前提が違うということならば今回の「クオリティメディアコンソーシアム」は勝手に内輪で盛り上がっている話だと帰着します。クオリティメディアが存在していく社会の方が健全で、それは民主主義が払うべきコストであり、結果的にはコストパフォーマンスがいいものだと考えます。

若干話が逸れますが昨年、「アメリカは内戦に向かうのか」(バーバラ・F・ウォルター著、井坂康志訳)を弊社で刊行いたしました。アメリカの著名な政治学者である著者が、20年に及ぶ徹底調査と歴史的な分析を行い、いわゆる「民主主義指数」を算出し明文化したものです。グラフはマイナス10からプラス10まであり、マイナスの数値が高いほど専制主義、プラスの数値が高いほど民主主義とされます。両極の国では内乱や内戦は起こりません。マイナス側にはロシアや北朝鮮が挙げられ、プラス側にはカナダやニュージーランド、ノルウェーなどの北欧諸国、アメリカも数年前まではここに位置していました。ところがトランプ大統領の登場や「Qアノン」扇動による前代未聞の連邦議会襲撃事件などを経てその後、アメリカのランクはプラス5にまで落ちています。このポジションは、民主主義でもなく専制主義でもありません。最も内戦の危機指数が高いゾーンです。
アメリカがランクを下げた背景には、政治家を含む複合的な要因がありますけれども、一方でインターネットやSNSが後押ししているということも考えられます。特にSNSは自分が見たいものしか見ない。局所的かつ断片的な情報によって、ユーザーがそれぞれの隔絶的な世界観を構築した結果、自分とは「異なる世界」を認められないようになっている。アメリカでは民主党支持者と共和党支持者の違いによって家族間でも話をしない、というような話も聞こえてきます。私は、日本もアメリカの背中をどんどん追いかけているような気がしています。アメリカほど危機的状況には至っていませんし、内乱まではいかなくとも、人々の自由はゆるやかに奪われ、民主主義が崩れている現状を「マズい」と思っています。
ものすごく大きく振りかぶると、我々が今頑張ることは、ひいては民主主義を守ることでもあります。あるいは、内戦の危機を回避すると言うと大袈裟なのでそこまでは言いませんが、日本の民主主義のためには——みなさんが自由に活動し自由に生きていける世の中を維持するためには——絶対にこの30メディア(「クオリティメディアコンソーシアム」加盟メディア)は必要だと。これ以外のメディアが不要だとは言いません。ですが、加盟30メディアはお伝えしてきたような危機意識のもと動いているというように見ていただければ幸いです。
*後日掲載する対談の後編では、企業が考えるべき「ブランドを守るための広告戦略」について語ります。
BI.Garageが有力メディア30社と共同運営し、日本のデジタル広告の品質の改善に注力する組織。広告掲載メディアと掲載広告双方のクオリティを追求できる唯一の広告配信ネットワークとして、最高品質の広告の提供を強化している。
*クオリティメディア宣言について
通知